多様な知性を育む好きな居場所が
必ず見つかる学校
浅野中学校・高等学校
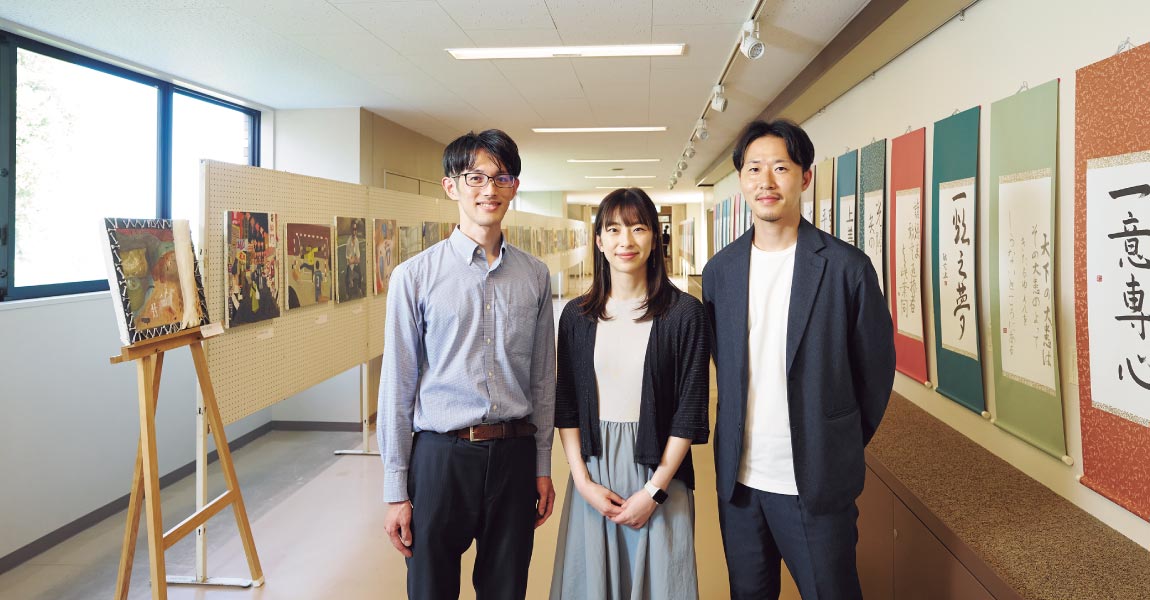
浅野中学校・高等学校は、卒業生の多くが難関大に進学する県内屈指の進学校だ。進学実績につながる主要5教科はもちろん、実技科目を含むすべての教科を大切にする校風が多様な知性を育んでいる。芸術などの実技科目を高1で終える進学校があるなかで、浅野は高2まで必修で学ぶカリキュラムを採用。高校の芸術科目は、美術と音楽、書道の3科目あり、生徒の希望に沿って選択する。それぞれに専任教員がいることも特色の一つだ。美術科の永浦俊哉先生と音楽科の上田恵先生、書道科の堀井広海先生に、芸術教育について話を聞いた。
美術は、実技中心のアカデミックな授業スタイルが特徴だ。中1・2は実技中心の授業で表現について学び、中3で多くの作品を鑑賞。多様な表現力や美術の歴史、文化など、基本的な知識を養う。高校では2年間かけて油絵の技法について専門的に学ぶ。美術で大切にしていることについて、美術科の永浦俊哉先生がこう話す。
「受験勉強を頑張ってきた本校の生徒は、問題の答えを導き出すことには長けていても、答えがないものについて、自由に表現することに慣れていない生徒が多いと感じます。美術の授業では、自分で考えて自分なりの答えを出していくことを大切にしています。その中で自分らしい表現やものの見方、センスを磨いてほしいと考えています」
音楽は、歌唱やリコーダー、ボディーパーカッションなどの「実技」、バロック時代から近現代まで、時代の流れを意識しながらの作品「鑑賞」、読譜力を養う「楽典」の三つをバランスよく学ぶカリキュラムとなっている。また中1の校外学習では、作曲家の三枝成彰氏がプロデュースする「はじめてのクラシック」のコンサートへ。クラシックを知らない生徒も楽しめるプログラムで毎年好評だ。音楽科の上田恵先生が言う。
「中学では全員が音楽を学ぶので、どんな生徒も興味を持てるような授業を心がけています。難しい中学入試を突破して入学した生徒が多い分、音楽の授業も理解度が高く、より高度な曲や楽器にチャレンジできています」
高校では、歌や器楽の実技をより専門的に学び、多様な視点から音楽について考えていく。歌はイタリア語・ドイツ語などの曲を原語で歌唱。器楽はトーンチャイムやキーボード、オカリナ、三線など様々な楽器に挑戦する。
書道は、同校オリジナルの良質な筆を使用している。中学書写では正しく適切な文字を書くことを目指すとともに、漢字や仮名の成り立ちや、筆や和紙といった伝統産業、書に関わる文化や歴史についても理解を深めていく。高校では、芸術科目として書道を学ぶ。高1は書の古典作品を学ぶ臨書を中心に取り組み、石や木などに文字を刻む篆刻や刻字にも挑戦する。高2では自分で題材を選び、自分らしい表現について考えながら作品を制作していく。書道科の堀井広海先生がこう話す。
「書道で最も大切にしているのが書に親しむこと。良い字を書くにはどうすればいいかを自分自身で考え、工夫していく中で、集中力や思考力、想像力を養っています。本校には書道室があり、落ち着いた環境で書に取り組むことができるのも魅力です」

施設が整う特別教室。部活動にも力を注ぐ
芸術科目で使用する施設・設備も充実している。美術室と音楽室は各2教室、書道室は1教室ある。それぞれが普通教室の1・5倍の広さだ。美術室には一人一台のイーゼルを用意。油絵を学びやすい施設となっている。京浜工業地帯やベイブリッジが一望できる校地には豊かな自然があふれ、風景画を描くには絶好の環境がある。
音楽室には4Kのディスプレイを設置。ウーハー内臓の音響システムにより、重厚感ある映像や演奏を視聴できる。また、手元を投影する書画カメラを芸術の全科目で取り入れている。作品制作で使用する材料の扱い方や、楽器の組み立て方、筆の動きなど、実際に作業している先生の手元を写すことで、生徒により分かりやすく説明できるという。
充実した施設・設備のもと、芸術系の部活動も活発だ。吹奏楽部は中1から高2の計38人が所属。横浜吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、県大会に出場を決めた。その他県内の吹奏楽コンクールやアンサンブルコンクール、毎年4月に実施する定期演奏会などに向けて練習に励んでいる。
美術部と書道部は10~15人の少人数で、運動部と兼部している生徒も多い。美術部は、部員が作りたいものを自由に制作。年1回、県の美術展中高特別企画に参加しており、2024年度は高2の4人が入賞・入選を果たした。作品が展覧会のポスターに採用された部員や、少人数ながら美術大進学を目指す部員もいるという。
書道部も一人ひとりが自分らしい作品づくりに取り組んでいる。文化祭では、書を使って空間を表現する一つの作品を全部員で作り上げていく。外部のコンクールにも参加しており、2024年度の高等学校書道展では個人・団体ともに県大会で優勝。5年連続で全国高総文祭に出場している。
最後に、浅野の良いところについて、永浦先生に聞いた。「勉強を頑張ることはもちろん、部活動や行事などを通して好きなことができるのが浅野の良さだと思います。この環境をフルに活用して、大学のその先で活躍できる幅広い力や人間力を持った人に育ってほしい。いろんなことに挑戦したい子にはピッタリな学校だと思います」



TEACHERS VOICE

本校の美術は、難しく、時間がかかる実技を取り入れているといわれます。中学では鉛筆デッサンや、サザエの貝殻や煮干しを粘土で摸刻する立体作品などに取り組んでいます。高校では油絵について専門的に学びます。外に出て、風景を見ながら油絵を描く実習があり、生徒には記憶に残る良い体験になっているようです。美術系の大学に進む生徒は少ないものの、大学受験の合間や卒業後に趣味で油絵を描いている人もいるようです。授業を離れても、美術に触れる機会をもってくれているのは、とてもうれしいです。

音楽は、長い歴史の中で確立されてきた便利なコミュニケーションツールの一つ。楽譜一枚あれば、言葉が通じない人とでも一緒に演奏することができる世界共通の知識です。中高時代にさまざまな音楽に触れ、音楽を通じたコミュニケーション力を高めてほしいと思います。中学3年間の目標は、楽譜を読み、楽器を演奏できるようになること。その上で、選択必修になる高校では、歌や器楽など実技を中心に学びます。他校ではほとんど扱わない三線を取り入れているのも特色の一つです。単旋律の伴奏と歌の弾き語りは難しいようですが、みんな楽しく取り組んでいます。

中学書写は手本の字を確かめながら書くアナログな作業が中心になります。週1回の授業なので飛躍的に上達することはないかもしれませんが、良い表現をするために試行錯誤する中で経験値を上げてほしいと思っています。高校書道では、書の芸術性について、その成り立ちなどを学びながら、自分らしい書表現を目指します。高1では書の古典作品から学ぶ臨書によって、書の技法や長い歴史の中で培われてきた芸術性について学びます。高2では自分が書きたい文字をどう表現するのか考え、さまざまな作品からヒントを得ながら自分らしい作品づくりに取り組んでいます。
取材日:2025.7.4
