身近な問題からデジタルリテラシーを習得。
自己肯定感が上がる「情報」の授業
日本大学櫻丘高等学校
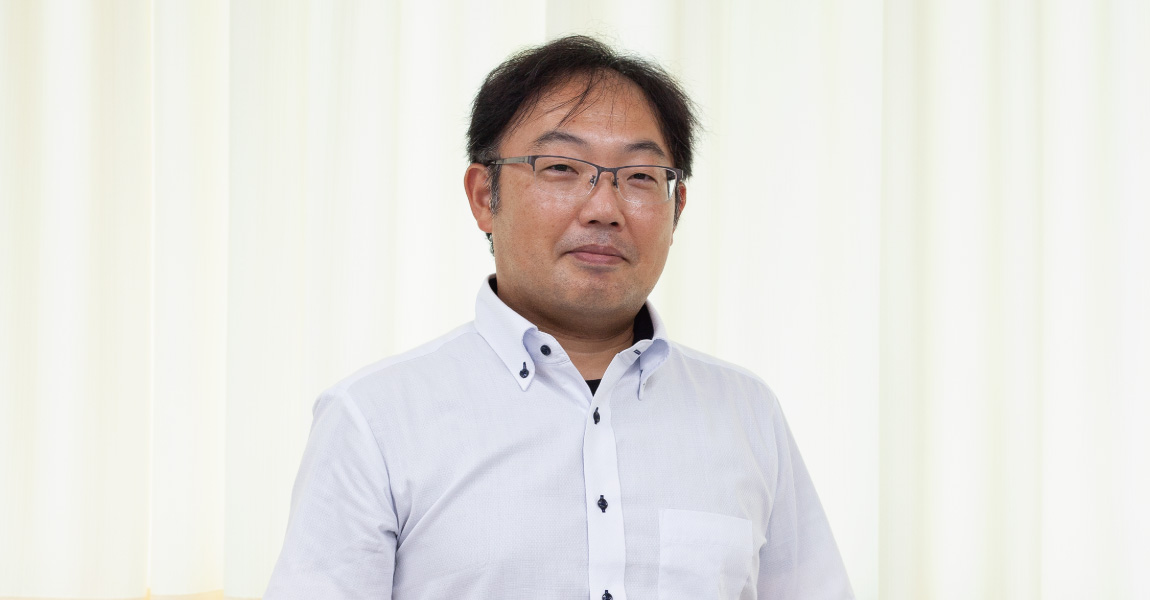
「櫻イノベーション」という学校改革を進めてきた日本大学櫻丘高等学校。新時代を生き抜く力を育成するため、ICT環境の整備にも取り組んできた。2022年度から高校で必修履修科目となった「情報Ⅰ」は、実習を中心に展開している。情報科を先導するのは情報科主任の田中忠司先生。もともと英語科だが、ICT推進のために情報科の教員免許を取得したという経歴の持ち主だ。田中先生に、授業の詳細やICT活用の状況について話を聞いた。
―情報科の授業では、どのようなことを学びますか。
田中 「情報Ⅰ」は、3年次に実施しています。問題解決能力を育成することが最終目的で、そのために、「情報リテラシー」「情報デザイン」「情報ネットワーク」「プログラミング」の4つの領域を学びます。「問題解決」というと社会問題をイメージするかもしれませんが、〝生徒一人ひとりの身の回りにある、ちょっと困ったこと〟を題材にしています。身近な問題を発見し、その改善に向けていろいろな角度から探究する力を身につけます。
たとえば、スマートフォンのアプリの使い勝手が悪いと感じたら、別の機能を付けたらどうなるかとか、ウェブサイトの画面で生産性が上がるような配置をどう調整するかといったことを考えます。今までは「できない」で終わってしまう生徒が多かったのですが、授業を受けた後は、生徒同士で解決策を提案し、情報を共有し合って、アイデアがどんどん膨らんでいます。
場合によってはアプリを作ることもあるため、そのツールとして、デザインの能力や、プログラミングの知識を身につけます。プログラミングは、ものごとを順序立てて考える能力を伸ばすことにも役立ちます。
―授業の具体的な内容を教えてください。
田中 すべての教科で、日本大学の建学の精神である「自主創造」をモットーとしています。そのため、情報科の教科方針は「Learn by Making」を掲げ、何かを作って実践を通して学びます。教室で黙々と学ぶのではなく、ペアワークやグループワークを取り入れ、いろいろな人の意見や考えに触れます。
授業は、反転授業で進めていることが特徴です。知識に関する事項はオンラインであらかじめ課題を生徒に配信し、自習で身につけます。その後、教室で実習を展開します。実際にリアルタイムで授業を行う空気感も大切にして、オンラインと実習を組み合わせています。
プログラミングについては、中学までに習った内容に差があるため、段階を追って、生徒一人ひとりの理解度をそろえます。まずオンラインゲームを使って、アルゴリズムの仕組みを理解します。その後、プログラミングの基本の3つの処理(順次処理、繰り返し処理、判断分岐処理)について実際に回線を使って理解を深め、ゲーム作りなどにも挑戦します。
課題として、毎年6月にグループワークで動画を作成します。今年は「中間テストまでに勉強した内容の解説動画を作る」というテーマでした。形式は自由としたため、黒板の前でただ解説するような動画ではなく、生徒のクリエイティビティが存分に発揮された作品がたくさん完成しました。中には、古文で勉強した登場人物になりきってインタビュー形式で構成した動画など、こちらの想定をはるかに超える作品もありました。最終的には鑑賞会を開き、クラスメイトの作品を見て、お互いの学びを深めていました。
授業では、教科書に載っていない内容も扱います。情報科は社会情勢に沿ったことを学ぶため、生成AIなど、新しい内容を取り入れる必要があります。毎年内容を変え、面白い授業になるよう考える必要があるので、教員も勉強が必要です。おかげで毎日刺激があり、楽しく授業をしています。

―情報科を通じて、生徒たちはどのように成長していますか。
田中 授業を始めたばかりの頃はパソコンの電源の入れ方も知らなかった生徒が、今では自らパソコンを起動して作業を始めているのを見ると、成長したなと感じます。
生徒たちは、授業を受けるごとに、どんどん目が輝いてきます。今までできないと諦めていたことに挑戦してみたら思いのほかできて、喜びを感じているようです。こうした成功体験を積み重ね、新しい自分に出会います。また、他教科の成績が芳しくない生徒が情報科で良い成績をとることがあります。クラスメイトに教える立場になって認められ、自己肯定感が上がっているようです。
さらに、授業で学んだことをほかの教科などにも生かしています。教室のパソコン以外に、ネットに接続できるLTEモデルのiPadを一人一台所持しており、文化祭や体育祭では、準備段階から当日の集計などに活用しています。情報科は自分たちの身の回りの問題を扱う学びなので、社会とのつながりを意識し行動に移せるようになっているところにも、成長を感じます。
私自身も、情報をもっと本格的に勉強したいと思い、今年、専修免許を取得しました。「先生も勉強している」という姿を生徒たちに見せたいという思いからです。
―櫻丘高校ならではの特徴はありますか。
田中 高校単独校のため、プログラミング学習についても中高一貫でのカリキュラムは組めません。幸い、日本大学文理学部に隣接しているため、大学のICT教育の情報が入ってきます。それをカリキュラムに取り入れ、大学に進学した際に、中高一貫校生と差が開かない力を付けさせたいと考えています。大学の学びを先取りできることが付属校としてのメリットです。
また、私が「Google forエデュケーション認定イノベーター/認定トレーナー」というグローバル資格を取得しており、Google Workspaceのエデュケーション版を教えられる立場であることも他校との違いです。先日はシンガポールに行き、アジアの教育者と交流してきました。ここで得た最新の情報を授業に還元しています。
学校全体の特徴として、櫻丘高校には、個性豊かな多様なタイプの生徒が在籍しています。たとえば、部活動で関東大会やインターハイに出場するような生徒もいます。さまざまな分野で頑張っている生徒から刺激を受けることで、自分の価値観を見直し、新しい自分へ一歩踏み出せる場所だと思います。
取材日:2025.9.12
