多彩な体験学習と少人数教育で
チャレンジ精神と論理的思考力を育む理数教育
カリタス女子中学高等学校
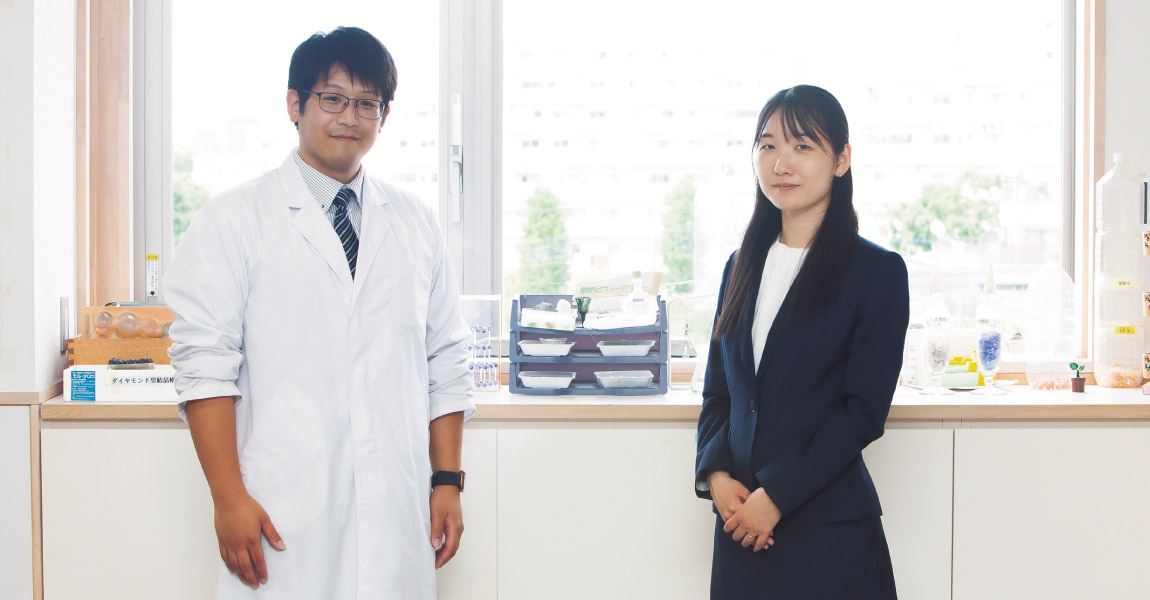
カナダ・ケベック州のカリタス修道女会を母体に設立されたカリタス女子中学高等学校。英語とフランス語の複言語教育や充実した探究学習などで知られるが、理数教育にも長年力を注いできた。生徒一人ひとりに合わせた指導を実現する少人数教育や、校外での多彩な体験学習が魅力だ。同校の理数教育について、理科の高實優先生と数学科の青木友香先生に話を聞いた。
―カリタス女子中学高等学校の理数教育の特徴を教えてください。
高實 理科教育のキャッチコピーは、「理科好きになる6年間」です。様々な理科的現象や実物を体感する機会を数多く用意することで、理科に興味をもってほしいと考えています。
中1〜2で週1時間行う「理科実験」は、1クラス20人程度の少人数授業です。3人1組で実験を行うため、全員が主体的に参加できます。生徒は楽しみながら取り組んでいます。
青木 数学は6年を通して、20人程度の少人数で授業を行います。そのため一人ひとりの学習状況を教員が把握し、きめ細かくサポートをすることができています。中学では習熟度別ではなく、いろいろな学力の生徒が混ざり合うクラス編成にすることで、生徒同士が教え合う環境を実現しています。
個々のレベルに応じた学習サポートも充実しています。数学が苦手な生徒には、毎週水曜日に指名制の学習会を実施しています。また、数学が好きな生徒には、マスタークラスを設置。グループでの演習問題やタングラムなど、数学の楽しさを実感できるワークを取り入れて、数学へのモチベーションを高めています。

―授業の中で大切にしていることを教えてください。
高實 単に実験を行うだけではなく、実験結果をもとに考察し、「なぜそうなったのか」を皆で話し合う機会を数多く設けています。それぞれの考えを共有することで、多角的な視野を養っています。
また、実験結果をレポートにまとめる際には、自分の考えを自分の言葉で表現していくことが大切です。正解・不正解に関わらず、そうしたトレーニングを重ねることで、"失敗を恐れずチャレンジする”姿勢を身につけてほしいと考えています。
青木 数学でも、間違えることを恐れて自分の答えを伝えられない生徒がいますが、「間違えることは悪いことではない」と繰り返し伝えています。生徒同士が話し合い、分からない問題にも知恵を出し合って最後まで諦めずに解こうと頑張る雰囲気があります。また、数学では小テストや課題の提出を頻繁に行っています。日々の課題を取り組むことがテストの点数に繋がったという成功体験が、数学への苦手意識の克服につながっています。
―理科や数学への興味・関心を高めていく、多彩な取り組みも魅力です。
高實 数多くの校外研修を実施しています。学校独自の体験学習として、多摩川・多摩丘陵でのフィールドワーク「Tamalogy(タマロジー)」があります。中1では多摩川での石や草花の観察や、生田緑地での地層の観察、中2では実際に川に入って生物採集を行います。中3では希望者を対象に、大師河原水防センターを訪問し、干潟の生物観察やヤマトシジミの個体数調査などを行います。身近な自然環境に接する機会が豊富にあります。このほか、多摩動物公園、江ノ島水族館、尾瀬国立公園などでの多彩な研修を用意しています。
また、本校の理科センターでは様々な生き物や植物を飼育しています。教員が理科にまつわるニュースを発信する「かえる通信」も、伝統的な取り組みです。理科で学ぶ内容を身近に感じられるように作成しており、生徒の視野をさらに広げています。
青木 数学では、理数教育研究所が開催する「算数・数学の自由研究」作品コンクール(通称:MATHコン)に中学生全員が参加しています。物を投げた時の放物線や、サイコロの出目の確率実証など、数学に関わる身近な事象をテーマにレポートを作成します。数学は座学に偏りがちですが、日常生活に目を向けて数学的要素を探す過程が、数学と実生活とのつながりを実感する機会になっています。また、自分の考えを学外の方に評価してもらうことも、生徒のやる気につながっています。
さらに、本校の数学センターには、マグネットや立体模型といった様々な教材が揃っており、生徒の好奇心を高めています。

―最近の大学入試では、女子の理系進学者が増加しています。
高實 本校も高校の理系選択者が増えており、学年の約3分の1が理工系・医療系学部に進学しています。女子枠や年内入試で合格する生徒も増えており、理科や数学への興味・関心が高まっているのを感じます。体験学習をきっかけに自然や生態系に興味をもち、自然科学系の進路を実現した生徒もいます。
生徒は、理科実験などを通して、物事を解決するために必要な論理的思考力を養っています。社会に出てからもその力を生かして、様々なことに挑戦してもらいたいと思います。
青木 少人数授業を通して問題にじっくりと向き合い、自分の考えを相手に伝える練習を重ねることで、思考力も磨かれています。高校生になると、生徒と教員で数学的な議論を重ね、一緒に問題を考えていける生徒もでてきます。
生徒には、「数学が苦手だから」という理由で理系進学を諦めてほしくありません。進路や自分のやりたいことを自由に選択するためにも、数学と向き合い、文理問わず様々な分野で活躍してほしいと思います。
STUDENT VOICE

Q.今までの体験で印象に残っていることは?
地学巡検で長瀞に行ったことです。資料館で予備知識をつけてから川沿いを歩き、資料館で学んだ事を体験するというプログラムでした。堆積する順番や岩石の結晶の形などについては中学受験で勉強しましたが、実際に見たことはありませんでした。小学生だった私は、図録を見て、自分なりに想像することしかできませんでしたが、スケールが大きすぎて上手く想像できず、苦戦したことを覚えています。実際に体験することで身近に感じることができ、イメージしやすくなりましたし、丸暗記していたことを自分の知識として深めることができました。
Q.おすすめの校外研修は?
特にオススメなのが尾瀬研修です。この研修ではたくさんの植物を知り、知識を深めることができました。植物分野を好きになるきっかけにもなりました。また、4年次に習った植生の知識も、実際の体験と結びつけることができました。授業などで習ったことを実際に体験することは、テレビで見ていた芸能人に会えたような嬉しさや楽しさがあります。カリタスには尾瀬研修以外にも理科を学ぶのが楽しくなる取り組みが多いので、オススメです!また、自然界は色々な要素が複雑に関係し合っており、学んだ理論が通用しないこともあります。そこも魅力の一つです。習ったこととなぜ違うのか、考えることも楽しいですよ♪

取材日:2025.5.28
