生徒の興味・関心を深めるプログラムが充実。
神話と日本文化について理解を深める出雲研修
國學院高等学校

交通アクセスが良い、緑豊かな文化的エリアに位置する國學院高校。多くの生徒が上位大学に進学する進学校だ。学園の母体となっている國學院大學は、「もっと日本を。もっと世界へ。」をキャッチフレーズに、日本文化への理解を深める教育・研究を行っている。同校もその基礎を身につけるために、勉強やスポーツ、学校行事など、バランスの良い全人教育に取り組む。生徒一人ひとりの興味・関心を深めていく多彩なプログラムも魅力だ。その一つ、出雲研修について国語科の小川澄人先生と、地歴公民科の鈴木聡史先生に話を聞いた。
國學院高校は1学年約600人と生徒数は多いが、一人ひとりの興味・関心に応える取り組みが充実している。その一つが希望者対象の体験学習だ。
体験学習には、東北・京都・出雲・沖縄への宿泊型の研修や、スキー教室、科学・文学について学ぶ日帰り研修、オーストラリア・カナダ・シンガポール・イギリスへの海外研修など、多彩なプログラムがある。
なかでも、高1対象の出雲研修は、国語科と地歴公民科が協力し合う、教科横断型の研修だ。校内にある学校博物館「日本文化史資料館」の所蔵品を題材にした映像教材を活用し、日本の文化財を守り、伝えていくことや、出雲の神話について事前に学習。それを踏まえて、現地で2泊3日のフィールドワークを行う。出雲研修の目的について、小川澄人先生がこう話す。
「グローバル化が進む中では、自国についてきちんと理解することが大切です。出雲研修では、神話を通じた日本の成り立ちについて勉強し、海外の人たちを前に日本がどういう国なのか発信できる知識を身につけてほしいと思います」

実際に体験することで学習意欲を高める生徒たち
文化史跡や遺跡が多い出雲は、古事記や日本書紀に記された土地が今も受け継がれている神話ゆかりの場所。研修では、「神話と日本文化」をテーマに出雲大社や古代出雲の史跡などを訪れ、日本文化への理解を深めていく。以前、同校で教鞭をとっていた出雲大社権宮司の千家和比古先生にも協力を仰ぐ、唯一無二の贅沢な企画だ。地歴公民科の鈴木聡史先生がこう話す。
「出雲は国譲りなどの神話が多く受け継がれてきた地。実際に足を踏み入れることで、その雰囲気を感じてほしいと思います。出雲大社の見学では、普段は一般の人が入れない場所まで千家先生に案内してもらいながら、出雲の人ならではの視点で、分かりやすくアカデミックな解説をしていただいています。生徒は感銘を受けながら話を聞いていますし、引率している我々もすごく勉強になります」
昨年12月に実施した出雲研修には、これまでで最も多くの生徒が参加。出雲大社や八重垣神社、風土記の丘資料館、女夫岩遺跡、神魂神社、荒神谷遺跡などの史跡や博物館を巡りながら見識を深めた。夜のミーティングでは、その日に聞いた話や感じたことなどを生徒同士で話し合い、共有することで、学びをさらに深めていった。
研修には、神話や日本文化について、より学問的に学びたい生徒から考古学に興味を持つ生徒まで、多様な生徒が参加。自分自身で体験することの大切さに気づくとともに、その後の学習への意欲を高める機会になったようだ。
また、日本文化史資料館には古墳時代の遺跡から発掘された出土品をはじめ、貴重な研究材料を数多く展示している。出雲研修での学びをさらに深めていく資料や文献もある。小川先生が言う。
「本校の学びは授業にとどまらず、体験学習や特色ある施設を活用してさらに広がっていきます。日本文化史資料館は、日本の歴史や文化をより深く学びたい人には魅力的な施設です」
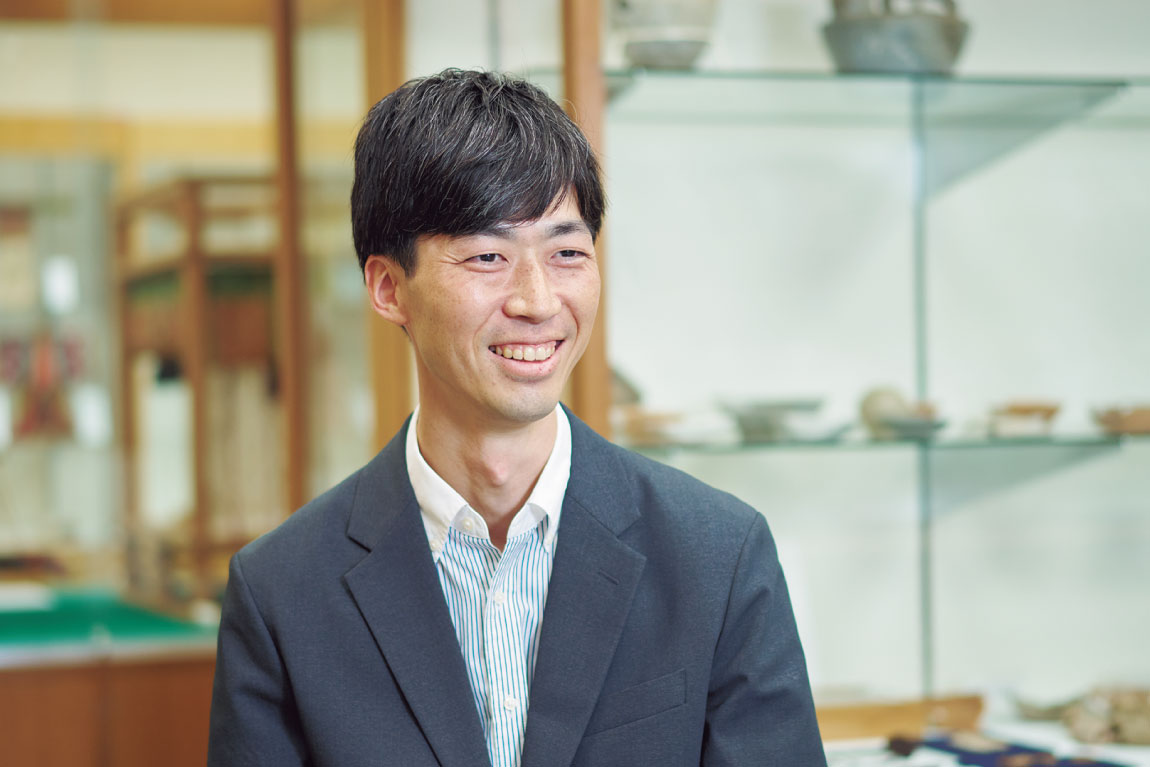
参加した生徒の声

—出雲研修に参加した理由は?
Aさん 子どもの頃から宗教学や神話学に興味があり、学術書などを読んで勉強していましたが、出雲には行ったことがなかったので、良い経験になるだろうと思いました。出雲といえば国譲りの神話の舞台。神話はファンタジーのイメージがありますが、当時の政治や宗教と何かしら関わりがあったようで、その部分を学術的に、より多角的に学びたいと思いました。また、出雲大社の権宮司の千家和比古先生が直々に案内してくださることも、参加を決めた理由です。
Sさん 私も、昔から日本の古代史に興味がありました。古事記や日本書紀、出雲国風土記に記されている神話は、それぞれ性質が異なるのが興味深く、その違いについてもっと詳しく知りたいと思いました。また、出雲の国引き神話には他の国の土地を出雲国にくっつけるエピソードがあり、そこに古代の国際性を感じましたし、神話が考古学的な学問とどう関連があるのか、出雲研修で実際に自分の目で見て感じ取りながら、考察を深められそうだと思い、参加しました。
—実際に参加してみてどうでしたか。
Aさん 千家先生には、神々と山々や河川との関係などについて、実際にその地にいる立場からご教授してもらいました。言語学的な解説などもあり、学術書を読んだだけでは得られない有意義な経験になりました。また、天地創造の神であるイザナミとイザナギの二柱が祀られている神魂神社も印象に残っています。この世を去り、黄泉の国に向かったイザナミを神として祀る日本人の死生観の独特さや、死も聖なるものとして考える価値観などが興味深かったです。境内も静逸さが満ち、神秘的な素晴らしい場所でした。
Sさん 国引き神話に出てくる神様がかけた綱や固定した杭は、現在の三瓶山や海岸線として伝えられています。どれが杭で、どれが綱だろうと思いながら出雲の地を歩く中で、飛行機も人工衛星もない時代にどうしてそんな壮大なスケールの物語を考えることができたのか。事前に出雲国風土記を読み、地名と土地の関係について勉強して行きましたが、実際に行ってみて圧倒されました。また、博物館では、荒神谷遺跡の358本の銅剣のレプリカを見ましたが、いざ目の前にすると、こんなにもたくさんの銅剣が見つかったことに驚きました。
—出雲研修でどんなことを学びましたか。
Aさん自分はアウトドアタイプではないのですが、現地に行き自分の五感を使って体験することで、得られるものがたくさんあることを実感しました。大学は人文科学系の学部を目指していますが、出雲研修を踏まえて、今後もフィールドワークを大切にしていきたいと思います。
Sさん 出雲研修で学んだのは現地調査の大切さ。研修で得たことは、言語学や民俗学など他の学問にも応用できると思います。資料などを読んで勉強することも大切ですが、自分で見聞したものの重要性を再認識しました。将来、大学では歴史学や言語学、民俗学などを幅広く学びたいと思っており、これからもっと勉強しようと、やる気が湧いてきました。

取材日:2025.9.18
